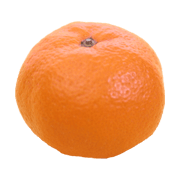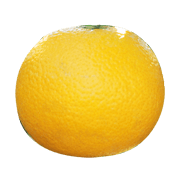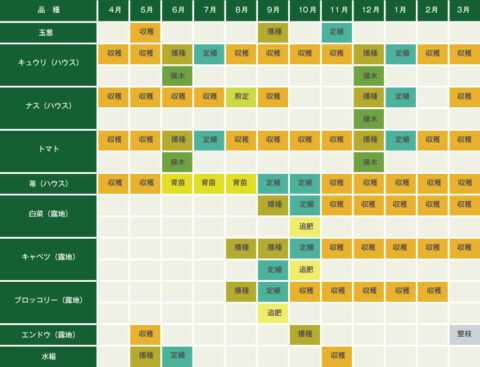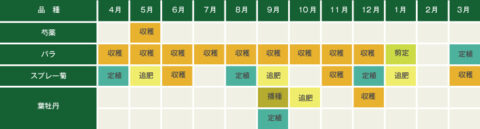豊かな自然に恵まれた和歌山県では、多種多様な農産物を生産しています。
JAわかやまでは、この地で生産された果物や野菜、花などの新鮮な旬の農産物が、皆さまのココロとカラダに潤いを届け、健康で豊かな暮らしを創っていけることを願い、「ココカラ和歌山」の名を付して、皆様のもとへ新鮮で安全・安心な農産物をお届けします。
和歌山県内では、それぞれの地域の気候などを活かし、多種多様な農産物を生産しています。
-

●キャベツ 紀の川河口に広がる水田裏作地を中心に、和歌山の温暖な恵まれた土地で育まれ、葉が柔らかく、爽やかなシャキシャキ感のある春キャベツが育っています。市場からは、産地として高い評価を得ています。
【出荷時期】
11月上旬~6月下旬(出荷最盛期は2月~5月上旬)
【選び方のコツ】
玉締まりがよく、外の葉の痛みのないものを選びましょう。切ってあるものであれば、葉と葉の隙間がなく、密着してるものを選びましょう。

●ハクサイ 紀の川河口に広がる水田裏作地を中心に、和歌山の温暖な恵まれた土地で育まれ、全品種が淡黄色を主とする黄芯系で、統一した栽培をしています。冬の体を暖める鍋物にかかせないもので、柔らかくて甘味のあるハクサイが育っています。
- 【出荷時期】
- 秋冬ハクサイ:10月下旬から2月下旬
春ハクサイ:4月上旬から5月下旬 - 【選び方のコツ】
- 光沢があり玉がよくしまり、茎の切り口が新しいものを選びます。胴がよく張っていて、しりが丸みを帯びている、手で持つとずっしりと重量感のあるものを選びましょう。

●ダイコン 紀の川河口の砂地や和歌浦湾の沖積砂地で育てられ、みずみずしくて光沢があり、肌は白くきめが細かく、肉質の柔らかいのが特徴です。特に名草地区で生産する青首ダイコンは、関西市場では「わかやま布引だいこん」としてトップブランドを誇り、令和3年5月に県内農産物で初の地理的表示(GI)保護制度に登録されました。
- 【出荷時期】
- 秋冬どり:11月中旬~2月下旬
春どり:4月下旬~5月下旬 - 【選び方のコツ】
- 光沢があり、色は白く、葉茎部(首)がきれいで割れや横ズミのないものを選びましょう。

●新ショウガ 海岸沿いの温暖な気候と豊富な地下水、紀の川下流に広がる良質な砂質土壌で栽培しています。繊維質が少ないため玉太りが良く、みずみずしくて美しい肌が特徴です。和歌山市は市町村別生産量で全国2位の大産地です。
- 【出荷時期】
- 5月中旬~10月
- 【選び方のコツ】
- 熱帯の植物なので、生のまま冷蔵庫に入れるのは禁物です。すぐに使いきれるなら冷暗所で保存。長期保存ならポリ袋に入れて冷蔵庫へ。使いかけの新ショウガは、ラップに包んで冷蔵庫に入れておくと、新鮮さが保てます。

●コマツナ 海岸沿いの砂地地帯を中心として、主に雨よけハウス栽培で生産されています。コマツナはアブラナ科に属する漬け菜の一種です。カロテン、ビタミンC、カルシウム、食物繊維を豊富に含み、アクが少なく下ゆでの必要がないので、軽くゆでてすぐに食べれば栄養を逃さず効率よく摂取できます。
- 【出荷時期】
- 8月上旬~翌年6月
- 【選び方のコツ】
- 葉の緑色が濃くて葉肉が厚く、葉の先までピンとしているものが新鮮です。茎の部分にハリがあり、みずみずしいもの、また、根に近い部分がしっかりしているものを選びましょう。葉柄が長くて細いものは、多少筋っぽくなります。

●ホウレンソウ 海岸沿いの砂地地帯や水稲の後作で栽培されています。ホウレンソウは栄養豊富な野菜の代表格。ビタミンはもちろん、鉄分やカルシウムもたっぷり含んでいます。
- 【出荷時期】
- 9月~翌年6月
- 【選び方のコツ】
- 葉が濃い緑色をしていてみずみずしいもの。茎が太く、茎の下がきれいな薄ピンク色のものを選びましょう。

●ブロッコリー 水田地帯の米の後作として栽培されています。ブロッコリーは野生のキャベツを品種改良して生まれたものです。小さい緑色のつぶつぶがたくさんついていますが、これは1つの花のつぼみです。それらが集まったものを「花蕾」といい花蕾と花茎の部分がブロッコリーとなっています。
- 【出荷時期】
- 秋冬どり:11月上旬~3月中旬
春どり:4月下旬~5月下旬 - 【選び方のコツ】
- 鮮やかで緑色が濃く、小さいつぼみが隙間なくぎっしり詰まり、丸く固く盛り上がったものを選びましょう。切り口がみずみずしく、茎が太く空洞でないものが良いです。

●ニンジン 海岸沿いの砂地地帯で栽培しています。ニンジンはβカロテンを多く含んでいます。これは、免疫力を高める効果や抗酸化作用があり、ガンや生活習慣病の予防に良いと言われています。
- 【出荷時期】
- 6月上旬~7月中旬
- 【選び方のコツ】
- 肩の部分が緑がかったものは避け、全体がなめらかなオレンジ色で皮に張りがあるものを選びましょう。葉の切り口の軸は小さい方が果肉はやわらかいです。

●トウガン 熱を吸収しやすい砂地地帯の土壌で栽培しているため、濃緑でつやがよいのが特徴。水分やカリウムを多く含み、体温を下げる効果が期待できます。夏が旬の野菜ですが日持ちはよく、冷暗所で保存すれば、冬まで貯蔵できます。
- 【出荷時期】
- 5月下旬~10月
出荷最盛期は7月~8月 - 【選び方のコツ】
- 表面に傷やいたみがなく、緑色の濃い鮮やかな色をしているもの。持った時に重たい方を選びましょう。

●ピーマン 砂地地帯のハウスで加温、無加温を組み合わせて栽培されています。京阪神にも1時間程度の輸送時間という立地条件を活かし、もぎたてのピーマンをお届けしています。
- 【出荷時期】
- 3月~8月
- 【選び方のコツ】
- 皮につやがあって色鮮やかなもの。肩が張っていて肉厚で弾力があり、ふっくらしたものを選びましょう。ヘタの切り口が黒っぽく変色していたり、皮にシワがあるものは少し鮮度が落ちています。

●タケノコ 東部地区の山東、安原の傾斜地帯が産地の中心となっています。土壌は、タケノコ栽培に最適な赤土土壌です。薄茶色の表皮で鮮度感があり、中の肉質は非常にやわらかいのが特長です。
- 【出荷時期】
- 3月下旬~4月下旬
- 【選び方のコツ】
- タケノコは穂先が土から出て日に当たるとえぐみが強くなり、風味が落ちます。日に当たったものは穂先が濃い緑色になるので、黄色、薄黄緑色のものを選びましょう。また、根元のイボが濃赤色になっていないもの。ずんぐりとした形で重みがあり、皮がつやつやしているものが良品です。

●キュウリ 業務用契約野菜の新規拡大品目として平成28年度から栽培がスタートしています。主に水田転作畑を中心に、作付けされています。
- 【出荷時期】
- 6月~9月
- 【選び方のコツ】
- 皮が濃い緑色で持ったときに重みがあり、太さが均一なものを選びましょう。果実が大きく曲がっていても味は変わりません。

●ナス 主に水田転作畑の露地で栽培されています。ナスは、淡白な味でクセがなく、味もしみ込みやすく、いろいろな料理に活用できます。
- 【出荷時期】
- 6月~10月
- 【選び方のコツ】
- 皮が濃い紫色で張りとツヤがあり、ふっくらしていて同じ大きさなら重みのあるものを選びましょう。ヘタの切り口がみずみずしく、トゲがピンととがっているものが新鮮です。

●ロメインレタス ロメインレタスは水田の後作として栽培されています。一般的なレタスと同じチシャ属の仲間ですが、その中でも、葉が巻かずに立った状態で成長する半結球レタスです。もともとエーゲ海のコス島が原産とされ、ローマを経由して西洋に伝わったとされています。
- 【出荷時期】
- 11月~1月
- 【選び方のコツ】
- 根元の切り口が小さめでみずみずしく、葉がパリッと張りのあるもの。芯軸がまっすぐなものを選びましょう。

●ミカン 東部の傾斜地帯が主な産地で、和歌山の温暖な気候と、水はけの良い土壌で甘くておいしいミカンが秋から冬にかけて味わえます。
- 【出荷時期】
- 10月上旬~2月下旬
- 【選び方のコツ】
- 重量感があって皮のきめが細かく、色が濃いものを選びましょう。皮をむいてみないと分からない場合もありますが、実の房の数が多いほどおいしいです。

●イチジク 東部地区の傾斜畑を中心に水田転作で、ハウスと露地で栽培されています。和歌山県のイチジク出荷量は愛知県に次いで全国第2位。栽培品種は「桝井ドーフィン」。果実の内部に赤いつぶつぶがたくさん詰まって独特の食感を生み出しています。
- 【出荷時期】
- 7月上旬~11月中旬
- 【選び方のコツ】
- ふっくらと大きくて果皮に張りと弾力があり、甘い香りのものを選びましょう。ヘタの切り口に白い液が付いているものは新鮮な証拠。お尻の部分が割れすぎているものは過熟の目印です。

●ウメ 東部地区の傾斜畑を中心に栽培されています。全国のウメの収穫高のうち、和歌山県はその6割を占めています。一年を通じて気温の変化が少なく、温暖で適度の雨量があり、日照時間も長く、ウメの栽培に適した気候・環境が揃っています。青梅で出荷している中心品種は、最高級種として知られる「南高」です。
- 【出荷時期】
- 5月下旬~6月下旬
- 【選び方のコツ】
- 丸みがあって香りがよく、傷や斑点のないものを選びます。梅干しにするならある程度熟した黄色いもの。梅酒用なら青く硬めのもの。カリカリの小梅を作るなら青みのある小梅がオススメです。

●モモ 東部の山東地区を産地の中心としており、水はけの良い緩やかな傾斜地と和歌山の温暖な気候が栽培に適しています。JAわかやまのモモは、顔を近づけた瞬間に広がる、甘く芳醇な香りが最高です。果肉からあふれ出す甘い果汁。夏果実の王様です。
- 【出荷時期】
- 6月中旬~8月上旬
- 【選び方のコツ】
- ピンク色がきれいなもので柔らかい産毛がしっかり生えているもの。形は割れ目を境に左右対称で丸みのあるものを選びましょう。皮に透明感があると食べごろです。

●カキ 東部地区の傾斜畑で甘柿は「富有」、渋柿は「刀根早生」・「平核無」を中心に栽培されています。
- 【出荷時期】
- 9月中旬~12月上旬
- 【選び方のコツ】
- ヘタがきれいで果実に張りつき隙間がないものを選びましょう。果皮がしっとりとして張りがあり、全体的に色づいているもの。また、持ったときに重みのあるものが良いカキです。

●わかやまジンジャーエール 和歌山は全国でも有数の新生姜の産地です。「紀州てまり野菜」のふるさとは、母なる川、紀の川の河口近く、太陽の光が輝き自然あふれる和歌山市です。それは和歌山市内の情熱農業家が、手間ひまを惜しまず我が子のように愛情をこめて育てたものです。
温暖な気候に恵まれた和歌山市で収穫される「新生姜」もそのひとつです。そして、さまざまな協力のおかげでこの「新生姜」の風味を活かしたジンジャーエールがここに誕生しました。
母なる川、紀の川の清流、燦々と降り注ぐ太陽の光をいっぱいに浴びて育ちました。
白とピンクのコントラストが鮮やかな新生姜。それは、一年中薬味としてよく目にする土生姜とは違い、繊維が少なく瑞々しい歯応えが特長です。ここ和歌山市では、古く大正時代から紀の川沿いの柔らかい砂地を活かした新生姜の栽培が始められたと言われています。きらきらと輝く柔らかな日射し、紀の川を流れる豊富な水量。収穫を心待ちにする人へ、大自然から年に一度の贈りもの。
●生姜佃煮 ごはんのおともでショウガ 和歌山の新生姜が全国有数の産地であり、特に生姜の甘酢づけについてはなじみがあると思います。生産農家では、生姜そのものを佃煮にしてよく食べられていますが一般の方にはあまり知られておらず、また生姜そのものの加工品は案外少ないため、この度、生姜をシンプルなかたちで提供できるよう、生姜佃煮をパック詰めにしました。生姜のピリリとした辛味とかつお節の旨味がマッチして、絶妙な仕上りとなっています。幅広い年齢層にご愛顧いただける一品です。一口食べるとごはんが食べたくなることから「ごはんのおともでショウガ」とネーミングしました。ぜひ、ごはんのおともにいかがでしょうか!

●しあわせみそ(金山寺味噌) 「金山寺味噌」。和歌山県外の人には、聞きはじめの方が多いと思います。調味料としての味噌でなく、温かいごはんにのせたり、酒の肴としてそのまま食べられるおかず味噌として、和歌山県では重宝され、お土産として密かに人気のある商品(和歌山県推薦優良土産品)。大豆・米・麦の原料すべてに麹を附け、地元産の白うり・ショウガなど様々な野菜を漬け込んだ、長期間保存食品でお手頃価格のごはんのお供です。
和歌山県の郷土料理に「おかいさん(茶がゆ)」があります。茶がゆやお茶づけのおかずとして、その相性の良さに「金山寺味噌」が愛され続け、食卓に欠かせない一品となっています。
地元食材を使い、保存料・着色料は一切加えていません。ぜひ、JAわかやまのしあわせみそ(金山寺味噌)をご賞味ください。
●こだわり米「つや姫」「にこまる」 JAわかやまのこだわり米は、環境・風土・気候に恵まれた和歌山市内で栽培する自慢のお米。農家さんが安全・安心をモットーに大切に育てたお米をぜひご賞味ください。
★こだわり米のこだわり★
1.和歌山県特別栽培農産物の認証を受けて栽培
農薬(節減対象農薬の成分使用回数)・化学肥料(化学合成窒素成分量)を慣行基準の50%以下で栽培し、自然環境への優しさも追求しています。
2.徹底した品質管理で安全安心
JAわかやまの検査員が1袋1袋米の品質を検査(検査米100%)後、食味検査を実施し、食味値76以上のお米のみを「こだわり米」に認定して販売しています。
※食味分析計:静岡製機(TM-3500)を使用。
★特徴★
【つや姫】甘みや旨みはもちろん、粘り気もあり、味のバランスが良く、見た目も良いお米。
【にこまる】丸くて大きく、粒ぞろいが良く、炊きあがりの艶がピカイチのお米。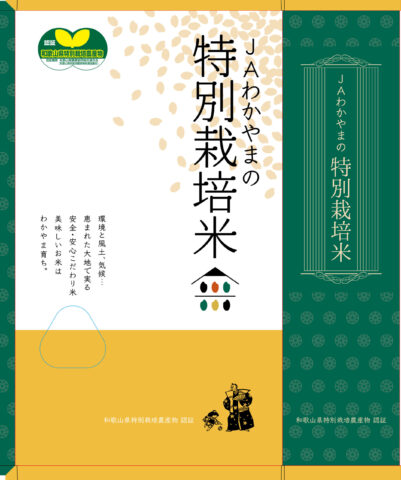
★節減対象農薬の使用状況★ ●品種名 : つや姫
〈使用資材名〉
〇クロラントラニリプロール・トリフルメタゾピリム・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤
( 用途:殺虫・殺菌 使用回数:4回 )
〇ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン粒剤
( 用途:除草 使用回数:3 回)
〇シラフルオフェン乳剤
( 用途:殺虫 使用回数:1 回 )
〇ジノテフラン水溶剤
( 用途:殺虫 使用回数:1 回 )●品種名 : にこまる
〈使用資材名〉
〇クロラントラニリプロール・トリフルメタゾピリム・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤
( 用途:殺虫・殺菌 使用回数:4回 )
〇ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン粒剤
( 用途:除草 使用回数:3 回)
〇シラフルオフェン乳剤
( 用途:殺虫 使用回数:1 回 )
〇アゾキシストロビン水和剤
( 用途:殺菌 使用回数:1 回 )
〇ジノテフラン水溶剤
( 用途:殺虫 使用回数:1 回 )
 |
●蔵出しみかん
海南市の下津町橘本にみかんを移植したのが、日本への柑橘類の導入として最も古いとされています。しもつ・海南営農生活センター管内を中心にみかんを生産しており、全国でもトップクラスの生産量を誇ります。特に主力となる「蔵出ししもつみかん」は、12月の完熟みかんを、糖や酸味のバランスが良くなるまで貯蔵したみかんです。 |
 |
●柿
海南市、紀美野町の傾斜地には柿が広範囲に栽培されています。特に美里支店管内には刀根早生、平核無などの渋柿と甘柿に属する富有が多く栽培されています。 |
 |
●桃
海南営農生活センター管内の高津地区を中心に栽培されており、贈答用としての需要が高く、光センサーで品質区分された特選品の「燦々」など、ながみねブランドとして確立しています。 |
 |
●キウイフルーツ
しもつ営農生活センター管内を中心に栽培されています。輸入品との競合もある中で、国内産の安全・安心さが評価され、消費は安定しています。 |
 |
●梅
管内全域で梅が栽培されています。健康志向のなかで消費が拡大しています。 |
 |
●ビワ
しもつ・海南営農生活センター管内の仁義・藤白地区を中心にビワが栽培されています。初夏を彩る果物として古くから地域に定着しており、特産果樹の一つとして位置づけされています。 |
 |
●山椒
特産品目として、また軽量化品目として山椒栽培が紀美野営農生活センター管内を中心に増加しています。 |
 |
●ミニトマト
主に海南営農生活センター管内を中心にミニトマト「キャロル7」をハウス栽培しています。 |
|
 |
●ウメ
小梅から出荷が始まり、続いて青梅、古城梅、南高梅などが出荷されます。 |
 |
●スモモ
スモモは果汁が多く甘酸っぱい味わいが特徴です。耕地面積が広い大石早生を主体として、サンタローザ、ソルダム、貴陽、太陽などの品種が続いて出荷されます。 |
 |
●モモ
夏を代表する果物、桃。 |
 |
●ブドウ
橋本市は巨峰、かつらぎ町はピオーネが主体で栽培されており、和歌山県下でも大きなブドウ産地です。 |
 |
●カキ
和歌山県は柿の生産量日本一を誇り、かつらぎ町、九度山町、橋本市と管内は全国有数の柿産地です。 |
 |
●キウイフルーツ
ビタミンCや食物繊維を多く含むフルーツとして知られています。 |
 |
●ミカン
11月中旬から12月末にかけて出荷される冬の定番果物。一言にミカンと言っても、極早生温州・早生温州・中生温州・普通温州と収穫時期によって少しずつ品種が変わって 出荷されます。 |
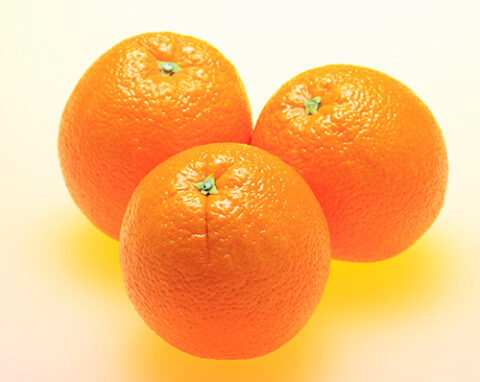 |
●ネーブル
種がなく、香り豊かで甘みが強いネーブルオレンジ。 |
 |
●イチゴ
フルーツの中でも圧倒的な人気を誇るイチゴ。言わずと知れたビタミンCの宝庫で、1日の必要量は中粒なら7粒でクリア出来ると言われるほど。 |
 |
●ハッサク
和歌山県はハッサクの生産量日本一。酸味の中にも程よく甘みがあり、独特のほろ苦さが特徴の柑橘。 |
 |
●不知火
「清見オレンジ」と「ポンカン」を交配して誕生した柑橘。濃厚な甘みとわずかに感じる酸味のバランスが抜群で大変人気のある柑橘です。 |
 |
●温州みかん
有田川が流れる左右の山や、海岸沿いの山々にみかん畑が広がります。 有田地域の農地の85%が柑橘類です。そのうちの85%が温州みかんです。 |
| ●ウメ
和歌山県はウメの生産量日本一。その中心は紀南地域ですが、有田でも少し栽培しています。梅干しや梅ジュースなど健康食品として日本人には欠かせません。 |
|
| ●キウイフルーツ
ニュージーランドの国鳥「キウイ」に似ていることから名付けられた。果肉が鮮やかなグリーンなので盛り合わせや、ケーキにも重宝される。国鳥「キウイ」も減っているとか。 |
|
| ●スモモ
最初は「酸っぱい桃=酸桃(すもも)」として軽視されていましたが、甘酸っぱくてジューシーに品種改良されて、和歌山県は全国2位の生産量。初夏の爽やかな果物。 |
|
| ●カキ
日本人に昔から親しまれている果物。和歌山県は生産量日本一。有田ではそれほど多く栽培されていませんが、家庭用として植栽しているほか、一部で市場へ出荷もしています。 |
|
| ●ブドウ
有田各地にもブドウの集団栽培地域があります。栽培歴史も長く、種類も豊富です。観光ブドウ園でブドウ狩りをしたり、市場出荷も盛んです。 |
|
| ●ビワ
和歌山県内では有数の産地として、海岸沿い(湯浅町田地区)で主に栽培されています。葉は冬でも落葉せず、柑橘と同様の常緑果樹です。 |
|
| ●ブルーベリー
ケーキやジャムなどの材料として近年人気があり、もちろん生食でもおいしい果実です。眼の健康維持に良いと言われています。 |
|
| ●イチゴ
みんなの人気果物、ケーキの王様。全国で栽培され、品種改良も盛んです。有田でも湯浅町や広川町で古くから栽培されています。和歌山県では「まりひめ」が自慢です。 |
|
| ●トマト
ビタミンCやリコピン、身体に嬉しい栄養がたっぷりのトマト。特に標高の高い清水や生石高原で栽培されているトマトは、濃厚な味わいが楽しめます。 |
|
| ●ミニトマト
施設栽培果肉ギッシリ、甘みたっぷりのミニトマト。お肉やお魚料理に添えるだけで、ちょっぴりイタリアンに。濃厚な甘みとほどよい酸味が食材と絡み合っておいしさ倍増。 |
|
| ●シシトウ
甘唐辛子とよばれるナス科トウガラシ属の野菜です。基本的に辛味のないししとうですが、成長の過程で暑さや水分不足などのストレスを受けると辛くなります。 |
|
| ●ニンニク
希少価値バツグンの生ニンニク。スーパーで見かけるほとんどは乾燥ニンニク。出荷は4月下旬!乾燥ニンニクでは味わえない、フレッシュな風味が自信の有田の生ニンニク。色んな料理に使えます。 |
|
| ●キュウリ
季節を問わず手に入るキュウリ。本来は6~8月が旬の夏野菜で、旬のものはビタミンCが2倍近くも含まれています。キュウリの95%は水分で、身体を冷やす効果もあるクールベジタブル。 |
|
| ●ヤマブキ
春を感じさせてくれる山菜の一つで、特有の香りとほんのりとした苦味が楽しめます。山野に自生しているものですが、一部地域で栽培されています。佃煮風に煮付けた「きゃらぶき」は簡単に作れて味も絶品。 |
|
| ●山椒
生産量日本一!有田の特産物「山椒」。生山椒は佃煮などに、乾燥山椒は香辛料や漢方薬に使われたり、うなぎの蒲焼きや麻婆豆腐、天ぷらやお肉料理など色んな料理に大活躍。 |
|
| ●スプレーマム
咲き方や色のバリエーションがとっても豊富なスプレーマム。お供えはもちろん、ブーケやウェディングの飾りなどいろんな場面で大活躍。大切な人への贈り物にもピッタリ。有田の花のリーダー。 |
|
 |
●南高梅
種が小さく、果実が豊富で皮が柔らかい南高梅。梅のトップブランドである「紀州みなべの南高梅」は、先人達から脈々と受け継がれてきた栽培技術を基本に、時代に合わせた工夫を加えながら、そのすばらしい品質を守ってきました。 平成18年には「紀州みなべの南高梅」として地域団体商標を取得しました。 (登録第5003836号) |
 |
●スターチス
生産量日本一!JA紀州では、紫、青、ピンク、黄、白色など、約60品種のスターチスを栽培しており、紫色の『紀州パープル』、青色の『紀州スター』はオリジナル品種です。 主産地は御坊市名田地区で、約30年前に栽培が始まりました。ハウス栽培で8月下旬~9月上旬に苗を定植し、10月下旬~6月中旬に収穫。北は北海道から西は岡山まで、出荷しています。 |
 |
●小玉スイカ
黒潮暖流の恩恵を受けた温暖な気候風土を生かし、管内の印南町、御坊市の名田、湯川地区で栽培され、5月中旬から7月下旬にかけて京阪神・中京市場を中心に出荷しています。 品種は「ひとりじめ7(セブン)」が中心で、甘くて果皮が薄く、大玉に近いシャリ感を持っています。また、まるごと冷蔵庫に入ることから大好評です。 |
 |
●うすいえんどう
うすいえんどうはJA紀州が日本一の生産量を誇り、粒が大きくホクホクとした食感が特徴です。和歌山県の特産ブランドとして「紀州うすい」の名で地域団体商標を取得しました。 |
 |
●木成り八朔(きなりはっさく)
管内の温暖な気候を利用して通常年末までにする収穫を年明けの2月上旬まで樹に実らせます。さらに収穫後一つ一つの実をポリ袋に入れて熟成させることで糖度と香りが増し、八朔本来の美味しさが味わえます。 |
 |
●優糖星(ゆうとうせい)
管内の印南町で栽培しています。 厳しい栽培基準を設け、糖度・食味にこだわったミニトマト作りに取り組んでいます。 糖度は8.0度以上です。 平成17年に「優糖星(ゆうとうせい)」は商標登録を取得しています。 |
 |
●赤糖房(あかとんぼ)
管内の印南町で栽培しています。 樹から房どりするのが特徴で、糖度は8.5度以上を誇ります。 平成17年に「赤糖房(あかとんぼ)」は商標登録を取得しています。 |
 |
●ゆら早生(ゆらわせ)
宮川早生の枝分かれとして、由良町で発見され、平成7年に品種登録されました。 極早生みかんの中でも、甘く美味しいと評価を得ています。現在、増殖増産に努めています。 出荷は10月初旬から中旬で、糖度11度以上でじょうのう膜も薄く、大変食べやすいおすすめ商品です。 |
 |
●デコポン(不知火)
不知火(しらぬひ)の中で、大きさ7㎝以上、糖度13度以上、酸度1.0以下のものだけを、 『デコポン』として出荷しています。 従来は2月上旬から中旬にかけて出荷していましたが、2月上旬まで樹に成らせ、収穫後1個ずつ包装し、3ヶ月間冷温状態で保存したものを、後期出荷タイプの「あじ姫デコポン」として、4月下旬から5月末にかけて出荷しています。 保存技術の向上により、甘さ・風味に加え、鮮度、品質も最高の仕上がりです。 |
 |
●さつき八朔(はっさく)
管内の、霜がおりない温暖な地域の特性を生かし、3月まで樹に実らせて、収穫後すぐに出荷します。 ゆっくりと熟すため糖度が高く、新鮮でもぎたての美味しさを味わうことができます。 充分な甘さに、ほどよい酸味、独特のにがみは控えめで、非常に食べやすく人気のある商品です。 |
 |
●ガーベラ
「希望」という花言葉をもつガーベラ。JA紀州は、和歌山県内1位を誇るガーベラの産地です。ピンク、オレンジ、イエロー、レッド、バイカラーなど約100種類の品種を栽培しています。 4月18日は、「ガーベラの日」です。 |
 |
●王糖姫(おとひめ)
管内の印南町で栽培しています。 糖度は7.0度以上の、長形ミニトマトです。 |
 |
●うめ
千年の歴史が物語る、日本の味・梅干し。紀州田辺は豊かな気候風土に恵まれた梅の里です。 |
 |
●みかん
紀南地方の温暖な気候と、太陽の恵みをいっぱいに受けて育つみかんは、梅に次ぐ紀南の特産物です。 |
 |
●晩柑類
JA紀南の晩柑では、味を重点とした“木熟シリーズ”が人気で、ポンカン・八朔・清見・ネーブル等、生産に取り組んでいます。 |
 |
●花き・花木
カスミソウやスターチンをはじめ、ガーベラやバラなど花きの施設園芸も盛ん。品種も多種多様で、消費者ニーズに沿った生産をしています。 |
 |
●スモモ
甘さとみずみずしさが特徴のスモモは、田辺市を中心に栽培されており、大石早生・ブランコット・ソルダムが中心種です。 |
 |
●レタス・水稲
管内では、とんだ地区からすさみ地区にかけて水稲の裏作として高品質レタスの栽培に向けて取り組んでいます。 |
 |
●紀州備長炭
備長炭の歴史は古く、平安朝(800年代)の頃に始まると言われています。弘法大使が唐(今の中国)から製炭技術を持ち帰り、和歌山県の各地に伝えられました。 |
 |
●なんたん蜜姫
本州最南端の町、串本町のJA紀南ブランドサツマイモ。その名の通り、焼き芋にすると蜜があふれ、ねっとりした食感はやみつきになります。幻のサツマイモとも呼ばれています。 |
 |
●くろしおいちご
和歌山県が生んだいちごのオリジナル特産品種「まりひめ」。その「まりひめ」を南国の温暖な気候の元で丹精込めて育てあげたのが「くろしおいちご」です。主に那智勝浦町太田地区で生産されています。大粒で、口に入れると甘く心地よい香りが広がり、程よい酸味がアクセントになっているのが特徴です。 |
 |
●ニンニク
管内のニンニクは、主に古座川町と串本町で栽培されています。栽培は平成23年より本格化し、平成27年には白いニンニクを熟成させた「黒にんにく」の販売が始まりました。熟成させることで独特の匂いがなくなり、ドライフルーツのような食感が楽しめます。また、熟成することで、ニンニクの持つ様々な成分の効能が増加するという特徴もあり、健康食品としても注目が集まっています。 |
 |
●音無茶
音無茶は、平安時代に京都から本宮に伝わったとされる歴史あるお茶で、田辺市本宮町で生産されています。平成26年にはペットボトル化が実現。ボトルには世界遺産「熊野古道」の文字や八咫烏(やたがらす)、熊野本宮大社のイメージを施すなど、一目で“本宮”とわかるデザインとなっています。 |